【食事のコツ①】ゆとりをもって食べる

人体は緊張状態で優位になる交感神経と弛緩状態で優位になる副交感神経がバランスを保つことで機能しています。通常、日中に勉強や仕事をしている時などは交感神経が働いて緊張状態にありますが、夜は副交感神経が優位になりリラックスモードに変わります。この自律神経のリズムを保つために食事は一定の時間に取ります。一般的に食べてから消化・脂肪の燃焼までには3〜5時間かかるとされているので、6時間間隔で食事をし、なおかつ就寝前の食事は睡眠の質を下げるので寝る3時間前までには夕食を済ましておきましょう。
また、食後の眠気や血糖値の上昇を軽減する意味でも、消化器官に負担をかけない食事が重要です。1口20回噛むことを目安に、ゆっくり落ち着いて食べることで副交感神経が優位になります。食事内容はセロトニンを摂取できるように「量より質」=栄養バランス重視にして、胃腸に負担をかけない腹八分目の量を心がけてください。
【食事のコツ②】糖質をとりすぎないように

ダイエットや筋トレのメソッドとしてお馴染みの「糖質制限」ですが、実は自律神経のバランスを整えるうえでも有効と言われています。
炭水化物に含まれる糖質は急激に体内の血糖値を上げます。すると、血糖値を下げるため副交感神経が膵臓を刺激し、インスリンが大量に分泌させます。食後に眠くなるのはインスリンの分泌で逆に低血糖になるためです。
このように、糖質をたくさん摂取すると副交感神経の活動量も増えるため、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経を整える糖質制限で重要なのは「大量に」とらないということです。炭水化物は体のエネルギー源ですので、自身の体調や体重に合わせて必要な量の糖質をとりましょう。その際には食物繊維を多く含む野菜から食べるなど、食事の順番にも気を使うと血糖値の急上昇を抑えられます。
【食事のコツ③】ビタミン・ミネラルも摂取する

不規則な食事や糖質の取りすぎを解消することで自律神経の乱れを整えられることはわかりましたね。では「体に良い」という印象が強いビタミンやミネラルはどうでしょうか。これらもやはり意識的に摂取したい栄養素です。
運動や睡眠改善と組み合わせて自律神経のバランスを取り戻そう!
自律神経を整えるには適度な運動や睡眠も不可欠です。運動不足気味だな、という方は、サイト内で紹介している簡単にできるさストレッチからはじめてみてくださいね。
元記事「自律神経を整える食べ物とは?食事から“セロトニン”を増やす方法」は2020年11月19日にBUSINESS LIFEに掲載されたものです。

自律神経を整える食べ物とは?食事から"セロトニン"を増やす方法 | ビジネスライフ(BUSINESS LIFE)
https://business-life.jp/active-health-for-office/18212ランチ後に眠くなりませんか?理由の一つは、消化の際に副交感神経が優位になって体を休息モードにしてしまうからです。ランチ後の眠気の例のように、自律神経は消化器官の活動と影響し合っており、食事の取り方によって自律神経は大きく左右されます。自律神経が乱れると、頭痛や睡眠障害など様々な不調を引き起こし、毎日の生活・仕事にも悪影響を及ぼしかねません。 では、自律神経のバランスを整えるためにはどのような食事を








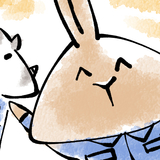






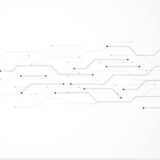









大学で心理学・精神医学を学び、その知識を深めるためアメリカに留学。帰国後、ヨガ・瞑想インストラクター、ダイエットジムReborn myself六本木本店店長・スーパーバイザー等を経て、2017年、日本初の疲労回復専用ジムZERO GYMのプログラムディレクターに就任。またダイエット指導経験から、独自の食欲鎮静メソッド「食事瞑想」を確立、ミスワールド日本代表の審査員やボディメイクも手掛ける。2019年3月、NHK WORLD JAPAN「Medical Frontiers」に出演し、世界160の国と地域にヨガと食事瞑想を伝授。著書に『エグゼクティブ・コンディショニング』等がある。