日焼け止めの種類と特徴
日焼け止めには、SPFなどの数値の違い以外にも種類の違いがいくつかあります。購入の際には、以下表を参考にしてみてください。
種類 | 特徴や使用感 |
ミルク | 日焼け止めの定番で、顔以外にも広範囲に塗る体の使用にも向いている |
クリーム | フィットしやすく顔への使用向き |
ローション | 使用感が軽くて伸びがよく、落とすのも簡単 |
ジェル | みずみずしくベタつきが少ないため、広範囲に使用する体向き |
パウダー | 粉状で簡単に使用でき、メイクの上からでも重ねづけができる |
スプレー | 手が届きづらい背中や他では難しい髪なども手を汚さず使用できる |
スティック | ベタつきが少なく手が汚れないため、外出時や塗りなおしに便利 |
内服 | 飲む日焼け止めで、塗るタイプとの併用が基本 |
タイプによって使用感が異なるため、使う場所やシチュエーションによって使い分けるとよいでしょう。
日焼け止めの使い方をシーン別で紹介
日焼け止めの使い分けについて、3つのシーンを例にご紹介します。これからの季節の室内・短時間の外出・レジャーの際など、使い分けの参考にしてくださいね。

■1日を室内で過ごす
室内で過ごす場合は、日焼け止めを使わない人も多いでしょう。しかし、部屋に窓があれば紫外線は室内にも入り込み日焼けをする可能性があります。特に窓際の場合、屋外の紫外線量を100とすると、おおよそ80とも言われています。
室内でも日焼け止めの使用は必須です。室内であれば、汗をかく可能性は低いため、使用感が軽く優しいもので問題はないでしょう。ミルクやローション・ジェルなどがおすすめです。もしも「ちょっとコンビニに行きたい」など、急な外出時にはパウダーやスティックがサッと楽に使えます。
■通学や短時間の買い物

短時間でも屋外に出るという場合には、クリームをはじめ、ある程度フィット感があり落ちにくいタイプを選びましょう。短時間だけど真夏で汗をかく場合には、ウォータープルーフの汗・水に強い製品がおすすめです。また、通学の場合は帰りに必ず塗りなおしをしましょう。日焼け止めは、汗や水だけでなく摩擦などでも落ちてしまいます。3~4時間おきの塗りなおしが推奨されているため、1度塗ったら終わりではなく定期的に塗りなおしが必要です。
■屋外の部活やレジャー

炎天下での部活や1日中外に滞在するレジャーなどは、最も対策が重要になるシーンです。このような場合、基本の顔・体への日焼け止めの使用だけでなく、スプレーで髪・頭皮の紫外線対策も行いましょう。髪や頭皮も紫外線によりダメージを受け、パサつきや乾燥を引き起こします。また、コストがかかりますが、特別な日のお守りとして「飲む日焼け止め」もおすすめです。製品によって特長や使用方法が異なりますが、抗炎症作用で赤みを起こしにくくしたり、肌へのダメージを軽減したりしてくれます。内服していても、必ず塗るタイプとの併用が必須になるため注意しましょう。
まとめ
日焼け止めの使用は、室内で過ごす場合でも必要です。日焼けして黒くなるだけでなく、将来の見た目にも大きな影響を及ぼし、最悪の場合は病気を引きおこす可能性もあります。
紫外線は、春からすでに量が増えてきます。夏だけ日焼け止めの使用をしていた人も、今年は早めの紫外線対策を始めてみませんか?
プロフィール
みなみ なみ
現役看護師WEBライター。
看護師として働きながら、ライター活動を行う一児の母。皮膚科勤務経験が長く、医療関連記事だけでなく美容記事も得意。
趣味は、グルメ・旅行・英会話。こどもに邪魔をされながら、日々執筆中!




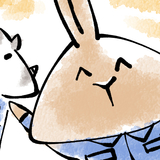






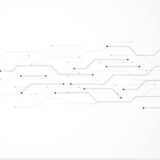









WattMagazine編集部 編集長