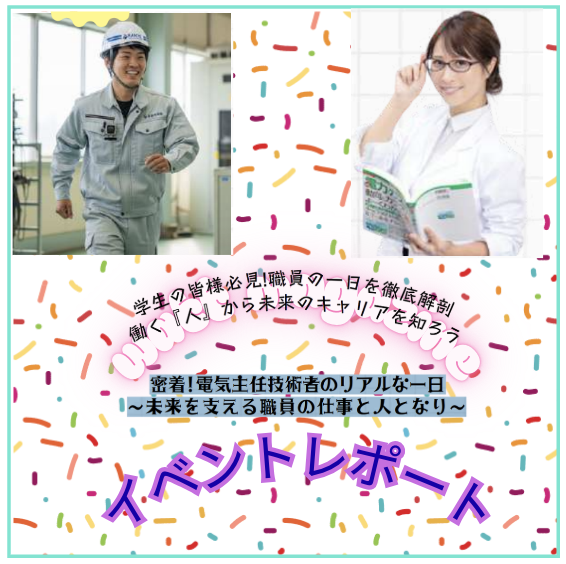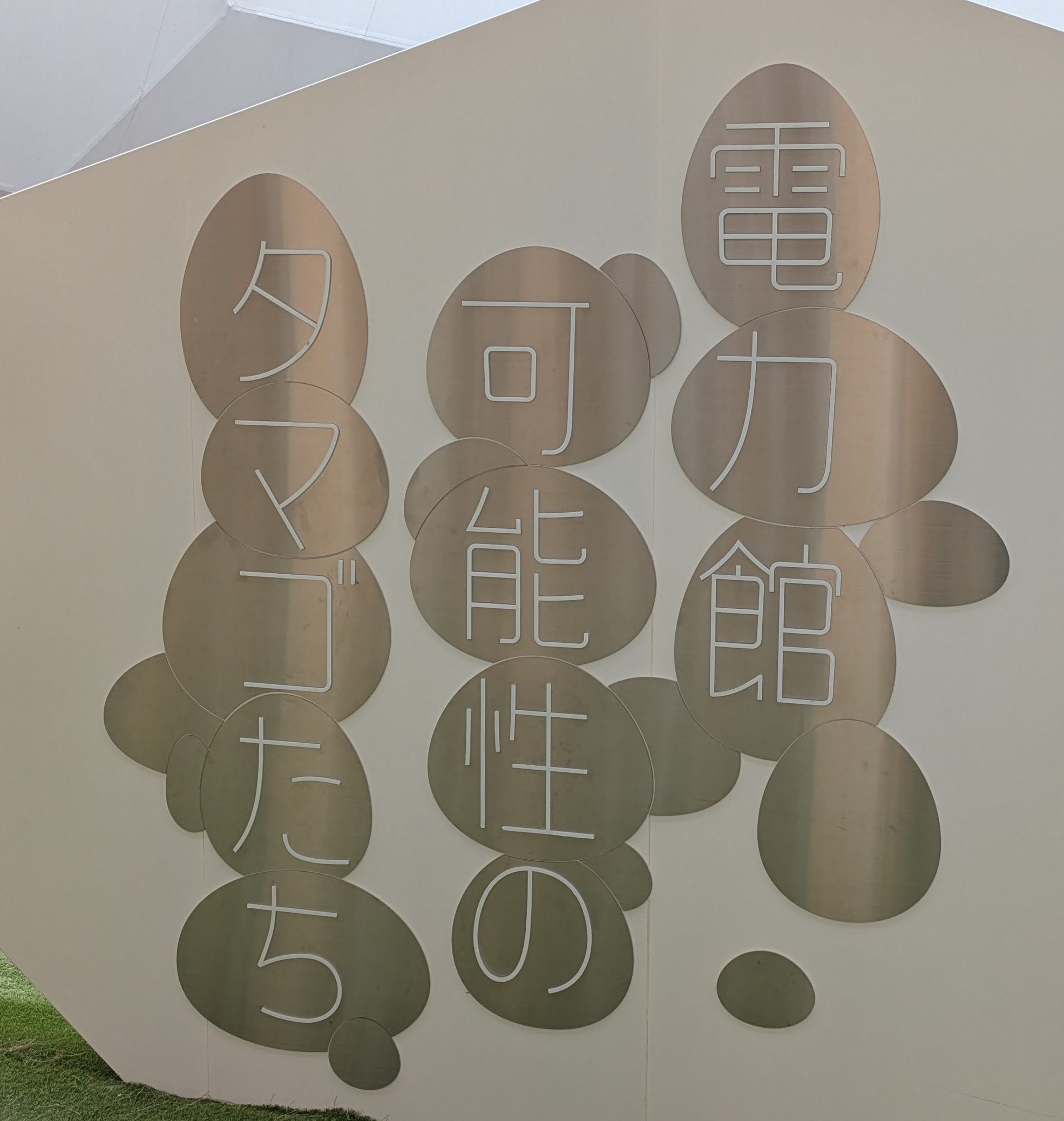現場レポート
2019年9月、台風15号が首都圏を直撃! 千葉県全域が停電! その時、男たちはどんな復旧活動をしたのか?
2019年9月9日、千葉県に台風15号が上陸。この台風により、首都圏およびその周辺地域は甚大な被害を受けました。特に千葉県全域での被害は大きく、多くの建物が停電に…。その復旧活動のため、多くの電気関係者が、災害地域に向かい、力を注ぎました。その団体のひとつが、関東電気保安協会。現場ではどんなことが起き、どんな困難に直面し、どう電気を復旧させたのでしょうか? 関東電気保安協会で災害時の作業を担当した3名に、お話を伺いました。
※撮影時のみ特別にマスクを外し、インタビューはマスクを着用したうえで、換気をした屋内で実施いたしました。
台風上陸前から本部に宿直。復旧活動は、台風上陸前から始まる!
――今回は2019年9月に上陸した台風15号によって発生した停電と、その復旧活動についてお話を聞かせていただければと思っております。まずは皆さん、自己紹介をお願いします。
芹澤裕一さん(以下、芹澤)「私は、関東電気保安協会の保安本部に所属しており、通常時は、電気設備の保安業務に関わる業務計画の立案等を担当しています。台風15号の災害時は、本部に交替で常駐し、現場で作業をする技術者たちに指示を出す、司令塔のような立場で業務にあたっていました」
岡村篤人さん(以下、岡村)「私と阿部は、建設部に所属し、電気設備工事の図面や見積を、作成をする業務を担当しています。災害時は千葉県の各地に向かい、復旧作業に従事していました」
阿部貴成さん(以下、阿部)「私たち関東電気保安協会は、関東1都6県だけでなく、山梨県と静岡県にも拠点を置いています。台風15号が去った後、各拠点で働く技術者(延べ700人)が、千葉県に集結し、復旧作業を行いました。その時は2人で1チームとなって、日中担当と夜間担当に別れて、交互に作業を実施。24時間体制で対応し、3週間で復旧活動が完了しました」
――当時、どのような復旧活動を担当されていたのでしょうか。
芹澤「復旧活動は、台風上陸前から始まります。数日前から首都圏に最強クラスの台風が上陸すると分かっていましたので、台風上陸前から事務所の事故応動に従事する宿直要員を増員し、台風が去った後の復旧活動に備えていました。台風が去って、いざ復旧活動となると、情報収集に集中。本部にいた私は、『〇〇市の□□へ行って欲しい』『●●の事業所で、燃料が足りていないから補給して欲しい』など、状況を加味しながら災害地で作業をする技術者たちに指示をしていました。なので、正確な情報を集め、現場で働く作業員がスムーズに働けるよう、適切な選択と決断を行うよう細心の注意を払っていましたね」
道が塞がり現地へ行けない、夜通し作業…。災害時ならではのトラブルや苦労
――実際に災害地へ行かれた岡村さんは、どのような復旧活動を行われたのでしょう。
岡村「復旧活動について話す前に、質問したいのですが、電気はどうやって皆さんの元に届くがご存じですか?」
――ええと……(答えが出てこず)
岡村「ざっくり分けると3つの段階に分けられます。(関東周辺では)東京電力さん等が電気を“発電する”、次に送電線や配電線などを通じて“送電する”、そして建物に設置している電気設備が“受電する”という流れです。私たちは最後のパートである“受電する”部分に関わっており、受電する電気設備に異常がないかをチェックしています」
阿部「電気設備に問題がないと判断できたら、建物に電気を通し、ここでやっと明かりを灯すことができるんです」
岡村「台風15号が上陸したことで、配電線経路が途絶えてしまったり、電気設備に不具合が起こったりして、多くの建物で電気が使えない状態になりました。そこで全国から、電力関係者が千葉県に集結。現地で配電線や電気設備を修理し、電気の復旧活動に努めたのです」
――通常時の作業と比べると、災害地での復旧作業は、どういった点が違いましたか?
阿部「普段は電気設備ごとに、担当者がいて、その担当者が日々、点検作業を行っています。そのため、通常はその電気設備に詳しい担当者がいますが、災害時は担当ではない者が電気設備をチェックすることになる。つまり、初めての電気設備に触れるため、手探り状態で作業することが多々ありましたね」
芹澤「保安協会のシステムには各電気設備の情報をまとめたデータが、“カルテ”のように保管されているんです。分からないことがあれば、現場に情報を共有し、作業しやすいようフォローしています」

――災害時ならではの苦労はありましたか?
岡村「作業をする現場に行くまでに苦労しました。ナビが案内する道を通っても、その道に木が倒れているので予定通りに進むことができず、迂回しなくてはならない。その迂回した先でも道路が塞がれていて、通れない…と現場に辿り着くまでが大変でしたね」
――1日に何箇所くらい電気設備をチェックするのでしょうか?
芹澤「1チーム、2~3箇所を担当していました。みんな必死で作業をしていました。宿直した日、私が寝る前に作業をはじめた夜班チームがいたんですが、朝起きて連絡してみたら、『まだ作業中です』と言っていて…。夜通し、作業をしていたんだなと。少しでも早くあかりを灯すために必死でした」
復旧活動が認められ、「電気保安功労者経済産業大臣表彰」を受賞
――そうした取り組みが評価され、翌年の2020年、関東電気保安協会は「電気保安功労者経済産業大臣表彰」を表彰されました。おめでとうございます! この賞は電気保安の確保に顕著な功績があった団体や個人を表彰するものです。
3人「ありがとうございます」
――なぜ受賞できたと思いますか。
芹澤「台風15号で停電被害を受けた時、災害地へ行き、復旧作業をしたことへの功労が評価されたのかな、と思っています。私たちの仕事は、電気設備の保安です。台風で建物が停電し、困っている方の元へ駆けつけ、迅速に対応する。そういった取り組みが、評価されたと思うと嬉しいですね」
阿部「当時はまだ、暑い時期だったので、停電でエアコンが使えず、みなさん、ジワリと体力を奪う熱さに困っていました。だから、電気が復旧し、空調が動いた時に、方々から『よかった』という安堵の声を聞くことができて、本当に嬉しかったです。そういう時、この仕事をしていて良かったと心から感じますね」
後編では災害の復旧活動をしていた現場では、どんな壮絶なドラマが起こっていたのかを明かしていただきます!
<関東電気保安協会>
1966年2月15日設立。関東の1都6県と山梨県・静岡県富士川以東の企業・家庭向けに電気の点検・保安業務を行っている一般財団法人。2019年9月に首都圏を直撃した台風15号により、停電したエリアの復旧活動をし、その功労が認められ、翌年には「電気保安功労者経済産業大臣表彰」を受賞した。
<執筆>
野田綾子
台風により停電、そして災害地での復旧活動。そこで見えてきた“仕事の素晴らしさ”とは?
ここ数年、毎年のように日本にやって来る大型の台風。それにより、河川の氾濫や土砂崩れ、そして停電が発生しています。そんな時、災害地に向かい、電気の復旧活動を…
消えた明りを取り戻せ! 復旧活動で求められる志とは?【中部電気保安協会座談会・前編】
2019年10月12日に上陸した台風19号。日本各地で多大な被害が発生しましたが、中でも長野県が受けたダメージは特に甚大なものでした。河川は氾濫し、多くの…

電気は1人で灯せない。“チーム電気”で挑んだ台風19号による復旧活動【中部電気保安協会座談会・後編】
2019年10月12日に上陸した台風19号。日本各地で多大な被害が発生した中、長野県が受けたダメージは特に甚大でした。河川は氾濫し、多くの建物や家が浸水被…







 一覧に戻る
一覧に戻る