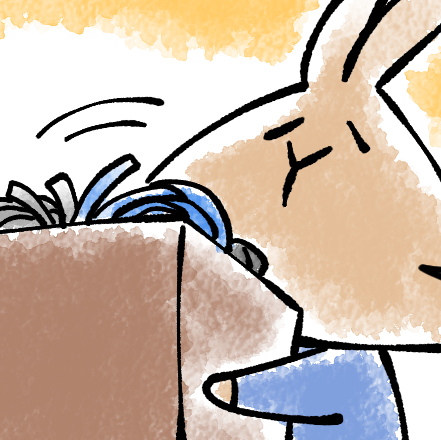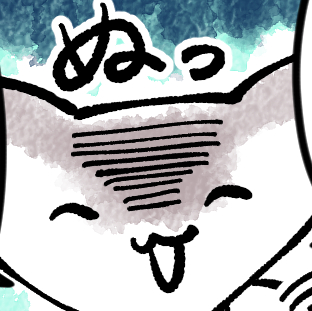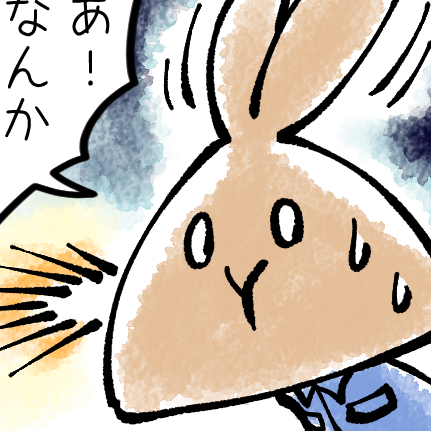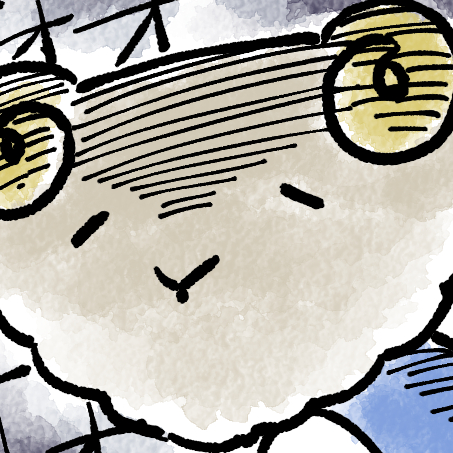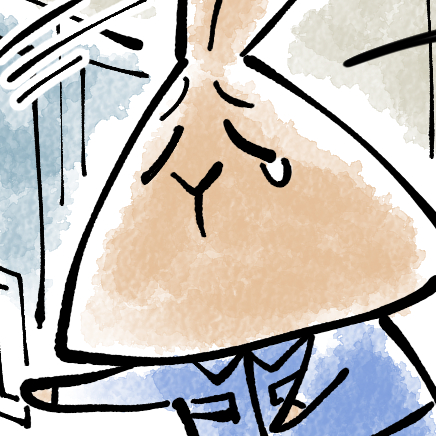電気 × マンガ
【関電工×Gakken】よくわかるシリーズ「電気のひみつ」を無料公開!
「学研まんがでよくわかるシリーズ」は小学生向けにさまざまなテーマをわかりやすく紹介しており、日本PTA全国協議会の推薦の図書です。非売品ですが全国の小学校や公立図書館に無料配布されており、電子書籍でも無料で読むことができます。
今回、関電工さんとGakkenさんが共同で製作した、「電気」をテーマにわかりやすく解説しているマンガ「電気のひみつ」を紹介いたします。私たちの生活に身近なテーマを取り上げながら、電気の原理や発電の仕組みなどを解説されており、小学生はもちろんのこと大人にもおすすめの一冊です。
電気の仕事はチームワーク
私たちが普段使用している「電気」が発電所から家庭まで電気人たちのチームワークで届けられていることが分かりやすくマンガ化されています。 プロローグでは、チームワークの大切さをラグビーに例えて紹介しており、小学生でもわかりやすい表現を使っています。 電柱や鉄塔の建設方法、送電線と配電線の違いなど、電気設備の詳細な解説や注目ポイントを電気設備工事会社である関電工さんだからこそ描けるマンガとなっています。
また、本編以外の「コラム」や「まめちしき」で私たちが疑問に思うことや子供からの「?」となるような疑問にもわかりやすく解説されています。 例えば、「なぜ、電線に止まっている鳥は感電しないの?」という質問などが掲載されています!
さらに知識を深めるため、電気の始まりから現代までの歴史や新しい技術や今、私たちが取組むべき課題に加えて未来の電気にも触れています。エネルギー問題がクローズアップされる中で、電気が発電されて私たちの生活の中で使用されるまでの仕組みを知り、今、何をやるべきかを考えるキッカケになる一冊です。 ぜひ小学生だけではなく、これから電気を学ぶ人、電気関係の仕事に就こうしている人、電気に興味のある人など電気人を目指す幅広い人たちに読んでいただきたいと思います。
小学生の学びにつながる!
実際、小学生の皆さんに読んでいただくと、 「文字だけではなくイラストがあって働く現場や電気設備の構造など、イメージがしやすかった。」 「鉄塔や電線などでの検査や点検などでドローンを使っていることは知っていたが、送電線を張るための工事にも使用していることは驚きであった。」 「電気の発見が静電気だったことは衝撃的だった。」 などとコメントしてくださいました!
本の概要
以下に本の概要について、記載しております。 気になる方は無料で読めますので、ご確認ください!

タイトル : 学研まんがでよくわかるシリーズ 195『電気のひみつ』 発 行 : 株式会社 Gakken ま ん が : 山口育孝 原 案 : 株式会社 YHB 編集企画 サ イ ズ : 菊判 ページ数 : 本文128ページ 目 次 : プロローグ ラグビーはチームワーク!? 第 1 章 台風被害で大規模停電 第 2 章 家で使う電気って…? 第 3 章 温室効果ガスの排出量を減らすために 第 4 章 建物の中の配線 第 5 章 電気の歴史 第 6 章 新しい技術の開発 エピローグ 電気の未来
本はコチラで読むことができます
「学研まんがでよくわかるシリーズ」は非売品のため書店での一般販売はありません。 『電気のひみつ』は2023年5月からGakken キッズネット内の「まんがひみつ文庫」や、「学研まんがひみつ文庫」にて無料で公開されています。
電気のひみつ | まんがひみつ文庫 | まんがでよくわかるシリーズ | 学研キッズネット
みんなは電気を毎日使っているよね。目に見えない電気ってどんなものなんだろう?電気が使えると、便利で快適な生活を送れるけど、電気はどうやって家に届くのかな?電気を安全に安心して使えるようにしてくれる人たちがいるんだ。いろいろな所でたくさん使われている電気はいつから使えるようになったのかな?この本を読めば、電気のことがとてもよくわかるよ。
電気のひみつ | 学研 まんがひみつ文庫
学研の「まんがひみつ文庫」○○○のひみつが読めるよ







 一覧に戻る
一覧に戻る