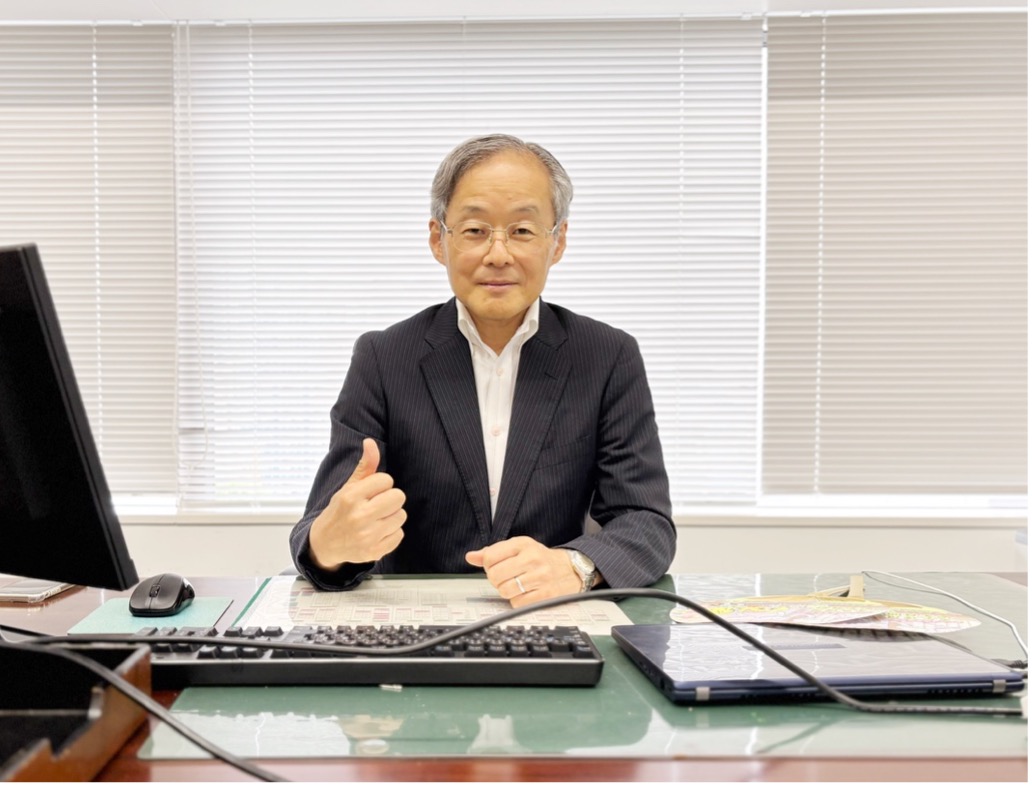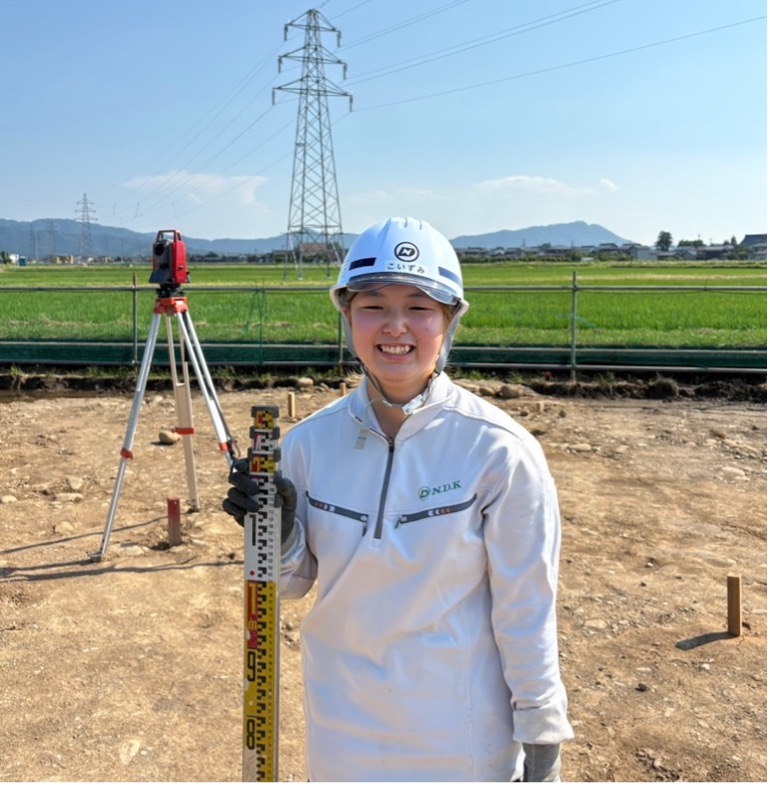現場インタビュー
【エッセンシャルワーカー対談 第三回】人が生きるために、そして生活を彩るために、欠かせない電気と食物。2つの業界から考える持続可能な未来とは
新型コロナウイルスの感染拡大により、注目を集めている「エッセンシャルワーカー」。電気設備の保安点検を行う電気管理技術者は、エッセンシャルワーカーとして多くの人々の生活を支えています。第三弾では農業従事者の小黒さんをゲストのお招きし、対談を実施。電気業界と農業の現場で働くお二人から、互いの働く現場と今後、そして電気と農業のこれからの可能性について語っていただきました。
目次
対談に参加されたエッセンシャルワーカーお二人のプロフィール(あいうえお順)
【参加者 #1】
小黒農場小黒 裕一郎さん

1979年2月生まれ。横浜出身。妻と子ども3人の5人暮らし。2005年に妻と山梨へ移住し、NPO農場で6年間有機農業に従事。2011年に独立就農し、自然栽培(無肥料無農薬)で野菜作りをしている。得意な品目はトマトとさやいんげん。 地域農業の将来の担い手を確保するために、農業者グループ「みずがきベジタブル 」メンバーとして、農業研修生の積極的な受け入れを行っている。
【参加者 #2】
電気保安管理業
田宮 伸光さん

1970年10月生まれ、埼玉県出身。 妻子供5人家族。
23年間、自動車メーカーにてプラントエンジニアとして従事したのち、2018年より独立。所有している国家資格をもとに、主体は電気設備管理と総合エネルギーの需給調整などのマネジメントを提供している。 今後も持続可能なエネルギーとそれを担う人材の教育に尽力したいと考え、自己啓発はもとより新人のOJT(オンザジョブトレーニング)を遂行している。
それぞれの業界に入った理由は…?
━━本日はエッセンシャルワーカー対談にご出席くださり、ありがとうございます。早速ですが、お二人の自己紹介からお願いします。
田宮伸光さん(以下田宮さん)「私のおもな仕事は電気を安全にお客さまの方で使っていただけるように、保安点検・管理をして、生産設備などの運用維持を図ることです。また、電気をより効率的に使用するアドバイスやマネジメントもしています」
小黒 裕一郎さん(以下小黒さん)「はじめまして、わたしは山梨県の北杜市で野菜の生産と小売店への出荷を主とした農業をしております。栽培規模は約2ヘクタールという面積―野球のグラウンド2つ分くらい―です。そこで日々、妻と私、そして研修生2名が作業しています」
━━お二人が現在のお仕事に就くことになったきっかけを教えてください。

田宮さん「私は以前、大手自動車メーカーに籍を置き、国内外で23年間、プラントエンジニアとして働いていました。仕事で世界の様々な国を訪れ、そこで様々な人々との生活をしてきた中で、人が共生していくうえで一番重要なものは、やはりライフラインだと改めて気づき、とくに電気の大切さを実感しました。
今、ほとんどの人が生活の中で日常的に電気を使っていますよね。そういった、なくてはならないものに携わっていきたいという想いがどんどん積もっていったのです。電気の仕事に携わるにはライセンスが必要ですから、在職中、必死になって勉強して資格を取得。現在に至ります」
小黒さん「私は26歳のときに神奈川から山梨に来て、農業をはじめました。もともと妻の方が農業に興味をもっていて、一緒にやらないかと誘われたことがきっかけです。私自身、アウトドアが好きだったこともあり、すんなりと入ることができました。きっかけはやや受動的かもしれませんが、今では農業が天職だと感じています」
田宮さん「農業は予測しづらい天候の影響も大きく受けますし、専門知識も欠かせません」
小黒さん「はい、毎日が勉強です。私の場合、新規就農といって、自ら農業という事業を興す形で業界に新規参入しましたので、研修を受けたり、独学で勉強したり、最初の10年は覚えることも山積みで大変でした。最近になってようやくちょっとした余裕がでてきましたが、野菜は生きていますから、まだまだ学ぶことも多くあるんです。そこが面白かったりもしますね」

私たちの生活は、“当たり前”を支える人がいることで成り立っている
━━お仕事の中でやりがいを感じること、また、やりがいを感じたエピソードなどございますか。
田宮さん「スイッチを入れると瞬時に照明がつきますし、ボタンを押せば機械が動く。多くの方が、電気はあってあたり前という感覚があるかもしれませんが、これはどのように電気が流れて動くのだろうとか、しくみについて考えたりする人はほとんどいないでしょう。電気は目に見えない危険が伴いますので、私たちのような技術者や専門分野の人間が必要です。自分たちの知識や経験を活かして、お客さまを助け、喜んでいただける。それがこの仕事のやりがいです。
電気は生活だけでなく、企業の事業にも欠かせないものですから、故障が起きたら復旧までは時間との勝負。工場などの生産が止まってしまうし、農家さんであれば、冷蔵庫が使えないなど、せっかく育てた野菜たちが傷んでしまう。お客さまの生活基盤に直結するものです。そんな緊張感のある場面で、自分たちの技術によって想定していたよりも早く修復できたときは、お客さまも喜んでくださいますし、強くやりがいを感じます。
私の仕事は、総合職というよりも専門職。そこは小黒さんの農業も同じではないでしょうか。専門知識を活かして、人々の生活を支えていく。それがこの仕事の最大の魅力。合わせて、自分の技術が、直接、利益につながることも大きな魅力だと思います」

小黒さん「農業も同じで、知識と技術、そして経験が、直接結果に結びつくところが魅力です。また、アウトドア好きな私にとって、自然の中で仕事ができるのも大きなポイントですし、自分で自分の食べ物を育てるというのも他の仕事にはない魅力です。ただ、田宮さんがおっしゃったように、農業は気候や天候の影響を直に受けますので、天候に恵まれないときは、収穫量も減ってしまいます。そこが大変だなという反面、乗り越えた時に得るものが多くあります。
ここ最近で一番印象的だったのは、2年前の梅雨のできごとです。その年は例年、7月の中下旬で終わるところが、8月の初旬まで大雨が続きました。私の農場では、トマトをおもに栽培しているのですが、トマトは雨が大嫌い。ですから、梅雨が長引いたことで、病気のトマトが増えてしまったのです。
今年はもう全滅してしまうかもしれないと思いましたが、諦めず丹念に世話をしつづけました。その結果、天候の回復とともに、トマトも元気を取り戻し、予定量の7割を収穫することができたのです。普段の収穫量と比べると少ないですが、0になりそうな状況から立て直すことができた。自分の手で復活させることができる、丁寧に育てればちゃんと応えてくれる。そういうところも農業の醍醐味かもしれません」

━━仕事へのモチベーションになっていることはなんでしょう。
田宮さん「私は自分が請け負った仕事には、付加価値をプラスすることを常に意識し、業務へ取り組んでいます。これからの電気業界では、電気の安定供給を維持するだけでなく、新たな取り組みにチャレンジして、お客様へ新たな価値を提供することが必要です。今までの仕事に加え、自分の技能や知識を活かして、お客様の利益や安全を向上させる。より、高度で幅広い提案ができるよう、日頃から勉強しています。また、自分の知識や技術が報酬に直結するのもモチベーションになっていますね」
小黒さん「私は自分の農業スタイルにこだわりを持っています。通常、肥料や農薬を使うところ、私は肥料や農薬を一切使わない、いわゆる自然栽培で農作物を育てています。これは、食べる人の健康に気を使った栽培方法で、私自身、アウトドアの活動をするなかで、自然環境や食、健康に気を使っていたことから、この方法を選びました。今後も農業を続けていく限り、この栽培法にこだわり続けたいと思っています。
体に優しいものは自然にも優しいので、今後さらに、自然栽培の農家さんが増えていってほしいなと思っています。そのため、これから農業をはじめようと志す若者を1人でも多く研修生として受け入れ、地域に、就農という形で還元しようと考えています。それが日々のモチベーションにもつながっていますね」
電気と農業にある共通点は「●●」
━━電気も農業も、私たちの生活にはどちらも欠かせないものです。そんな共通点をお持ちの農業と電気業界に携わるお二人ですが、お互いの目には、それぞれの業界がどのように映っているのでしょうか。
田宮さん「実は私の親族が農園を経営していることもあり、私も時間があるときにお手伝いに行きます。親族はよく“コスト削減”について頭を悩ませていますが、小黒さんが何か取り組んでいることはありますか?」

小黒さん「自然栽培という栽培方法では、肥料・農薬をあげないので、一般的な栽培方法に比べて、収穫量は6~7割になります。つまり、収穫が減るぶん、収入が少ない。そのため、農業をはじめた頃からコストについてはかなり細かく考えてきました。逆に、いかに稼ぐかというよりも、いかに使わないかを考えることが多いですね」
田宮さん「なるほど。農業の仕事と私たち電気の仕事と大きく異なる点は、生産しているか、否かにあると思います。私どもは知識や経験をもとにリスクを予測し、人へ利益や付加価値を届けますが、農業は生産したものがそのまま利益にも直結します」
小黒さん「こういったら本当に失礼かもしれませんが、電気業界は農業と同じで、地味な業界です。たとえば同じエッセンシャルワーカーと呼ばれる職業でも、お医者さんは若い人が将来の夢に挙げる職業ですよね。しかし、電気や農業を将来の夢にしている人はそう多くはないはず。ですから、私たちの業界に従事する人たちは、本当に好きか、使命感や責任感が強いかだと思うんですが、田宮さんはどう思われますか」
田宮さん「個人的な価値観の問題もあります。いわゆる“3K職場”と言われるものにはいろいろありますが、体を動かす仕事が好きな人は好きでしょう。小黒さんの言うとおり、私はそもそも花形よりも縁の下でお客さまと共生し、信頼を育むスタイル。しかし、地味な仕事をしているからこそ、どっしりとした大輪が花開くのだと思うのです」

小黒さん「電気も農業も、世の中のすべての人に関係していること。そういう意味では、両業界とも社会に不可欠であるという共通点があります。不可欠なものを届けるということは、安心感を提供することができるということでもある。社会のために、人のためにある仕事って、本当に素晴らしいと思います。ちなみに、田宮さんの業界はコロナによる影響を受けましたか?」
田宮さん「そうですね、仕事自体に影響はありませんでした。そういうさまざまな環境に左右されないのも共通点かもしれませんね」
小黒さん「おっしゃる通りですね。私はというと、巣ごもり需要や健康志向の方が増え、食への関心が高まったのか、有機栽培野菜のニーズが増えたように感じます。どんな環境下においても、食は欠かせないもの。この仕事を選んで改めてよかったなと実感しました。今のようなwithコロナ時代に求められることは、『自立と調和』だと思っています。
何が起きても自分の力で立てるぐらいの強い精神、情報に惑わされないことが重要です。
私個人としては、良い意味でこだわりを捨てました。こだわりすぎると、どこかで支障が出てしまう。自分のこだわりを持つことは大事ですが、こだわりを精査することも同じくらい大事なことです」
田宮さん「たしかに。これからは自分軸を持つこと、そしてバランス力が重要になっていくと思います。それは仕事だけでなく、自分を成長させるためにも、です」
持続可能な未来に向けて−電気と農業のこれからを語る
━━農業と電気の未来について伺います。最近では、IoTで畑や農作物の様子をモニタリングしたり、異常検知のアラートで知らせたり、というソリューションが生まれています。電気×農業という視点で、今後どのようなサービスが拡大したり、誕生したりすると思われますか。
田宮さん「電気×農業という視点で言いますと、ソーラーシェアリングがこれからさらに拡大していくと考えています。私が取り組んでいる分野に、自分たちの手で太陽光から電気を生み出し、それを消費して生産品につなげていく「営農型太陽光発電」があります。これは再生可能エネルギーに着目した取り組みで、農林水産省も積極的に支援を進めているものです。

たとえば、トマトやブルーベリーを作っている畑の上に屋根型の太陽光発電のパネルを並べ、半分は自家消費し、もう半分は電力会社に販売することも可能です。カーボンニュートラルな社会に向けて、CO2の削減にも取り組んで行かなくてはなりませんし、農業ならではの持ち味が生かせるソーラーシェアリングは面白いのではないでしょうか」
小黒さん「私も農場内でできる電気の自給に興味があって。食料の自給をテーマにイベントを主催していることもあり、電気も自分たちで作れたら面白いなと考えていました。 昨年まで北杜市の農業委員を3年間勤めていたため、営農型の太陽光発電についてよく勉強したのですが、個人的に心配なのはその下で育つ農産物への影響です」
田宮さん「営農型太陽光発電は、型にはまったやり方はなくさまざまなものに合わせて調整できるのもメリットです。栽培する作物に合わせて、温度や日光の当たり具合といった些細な調整も可能です。
ただ、ソーラーシェアリングが広がらない理由の一つに、高額な導入コストが挙げられます。これについては現在、補助金制度が各種ありますから、うまく活用していただくことで、将来的に自然を守りつつ、持続可能な地域の循環モデルが構築できるでしょう。兼業農家さんにはお勧めできませんが、小黒さんのように将来的に長期レンジで農業に取り組んでオーガニック野菜を作っていくという強い意志をお持ちでしたら、農業の未来を広げていく手段の一つとして、面白い取り組みになるのではないでしょうか」

小黒さん「ありがとうございます。ぜひ今度詳しいお話を聞かせていただきたいです!」
田宮さん「また、システムなどで自動化したり、効率化したりすることも重要ですが、電気も農作物も人が生きるために必要不可欠なものだからこそ、業界を守り、維持するために人材育成が必要だと考えています」
小黒さん「同意です。先ほどもお伝えしたように、農業研修生を募集し、育てることに注力しています。現在はコロナの関係でストップしていますが、農業体験のイベントも開催していました。実際に体験いただくことで、農業本来の良さが伝わりますし、土に触れることの楽しさ、自分で育てる喜びを実感して、『やってみたい』へとつながると考えています」
興味を持ったものへ、突き進め!
━━このメディアを見ている10代〜20代の方にメッセージをいただけますでしょうか。
田宮さん「今はSNSなどで情報がすぐに手に入る世の中になりました。ただ、見方を変えると、不要な情報まで簡単に得られる世の中になったとも言えます。そんな今だからこそ、たった一つの興味やこだわりを追求することが非常に大事だと思うんです。これは仕事だけでなく、生活習慣もそうです。興味がなければ、人はなかなか成長しません。ですから、電気や農業だけでなく、自分が興味を持ったものに対して、どんどん突き進んで、極めていっていただきたいなと思います」
小黒さん「私も同じで、興味・関心の赴くままに歩んでほしいです。自分の心に正直に生きて、やりたいことを貫いてください。私は、大学を出た後に就職せず、自転車で日本を一周しました。一流企業に就職した大学の同期からは呆れ声が聞こえてきましたが、そんなことを気にせず、さらに海外へ自転車を走らせ、そのうち農業に出会いました。自分の軸をぶらさなければ、人生を乗り切ることができる。自分の足で、自分の道を作り、歩んでいきましょう」
エッセンシャルワーカー対談シリーズ

【エッセンシャルワーカー対談 第一回】 電気と医療の現場で働く両者が気づいたインフラを支える仕事の共通点とは
新型コロナウイルスの感染拡大により、注目を受けた「エッセンシャルワーカー」。電気の現場で働く人はもちろんのこと、医療現場で働く人もまたエッセンシャルワーカ…
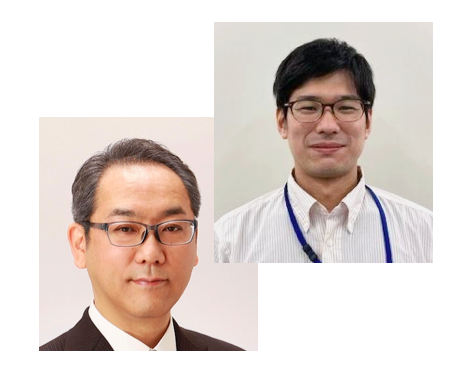
【エッセンシャルワーカー対談 第二回】電気と教育の現場はDXが進む…? エッセンシャルワーカーの働く未来を考えてみた
新型コロナウイルスの感染拡大により、注目を集めている「エッセンシャルワーカー」。電気設備の保安点検を行う電気保安技術者は、エッセンシャルワーカーとして、多…







 一覧に戻る
一覧に戻る