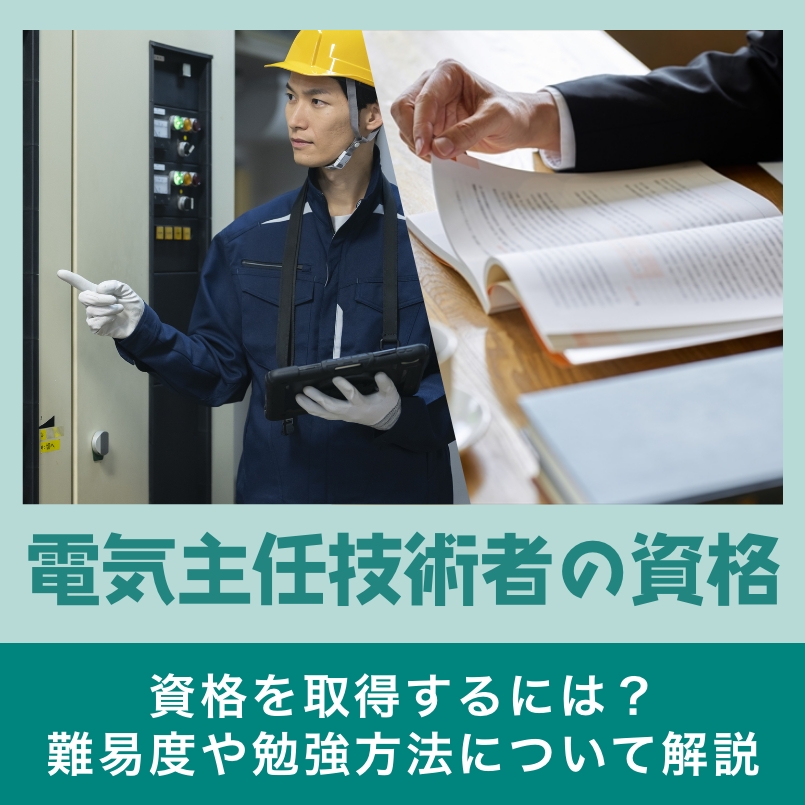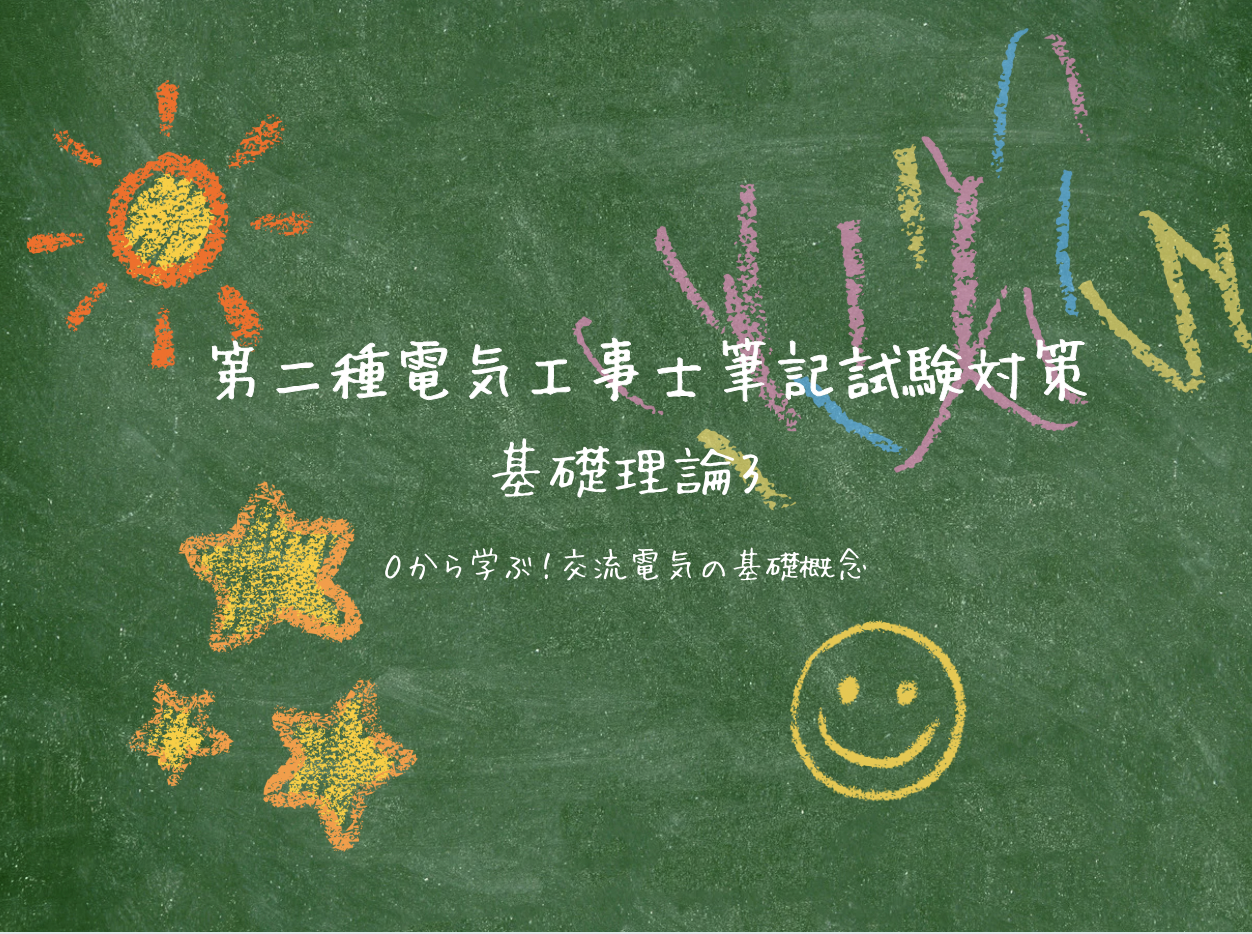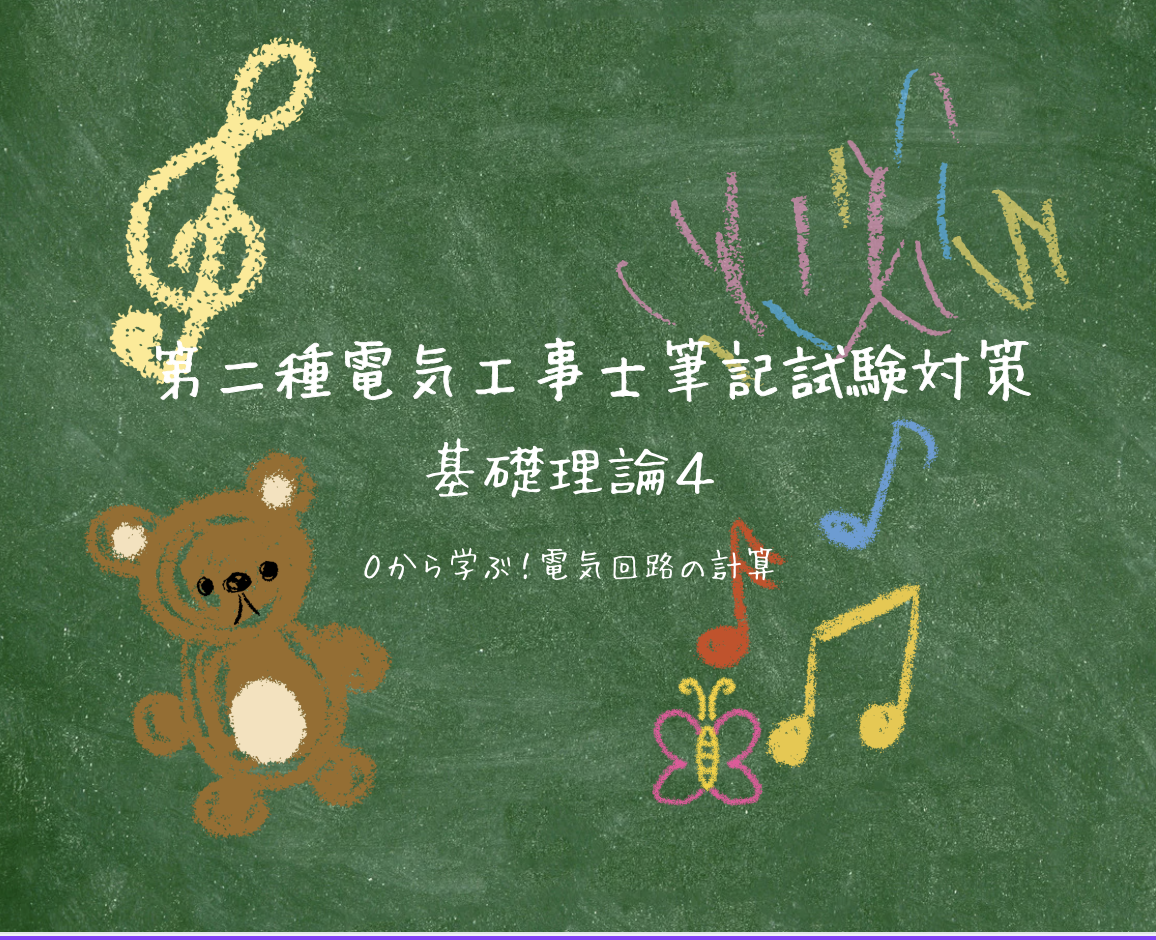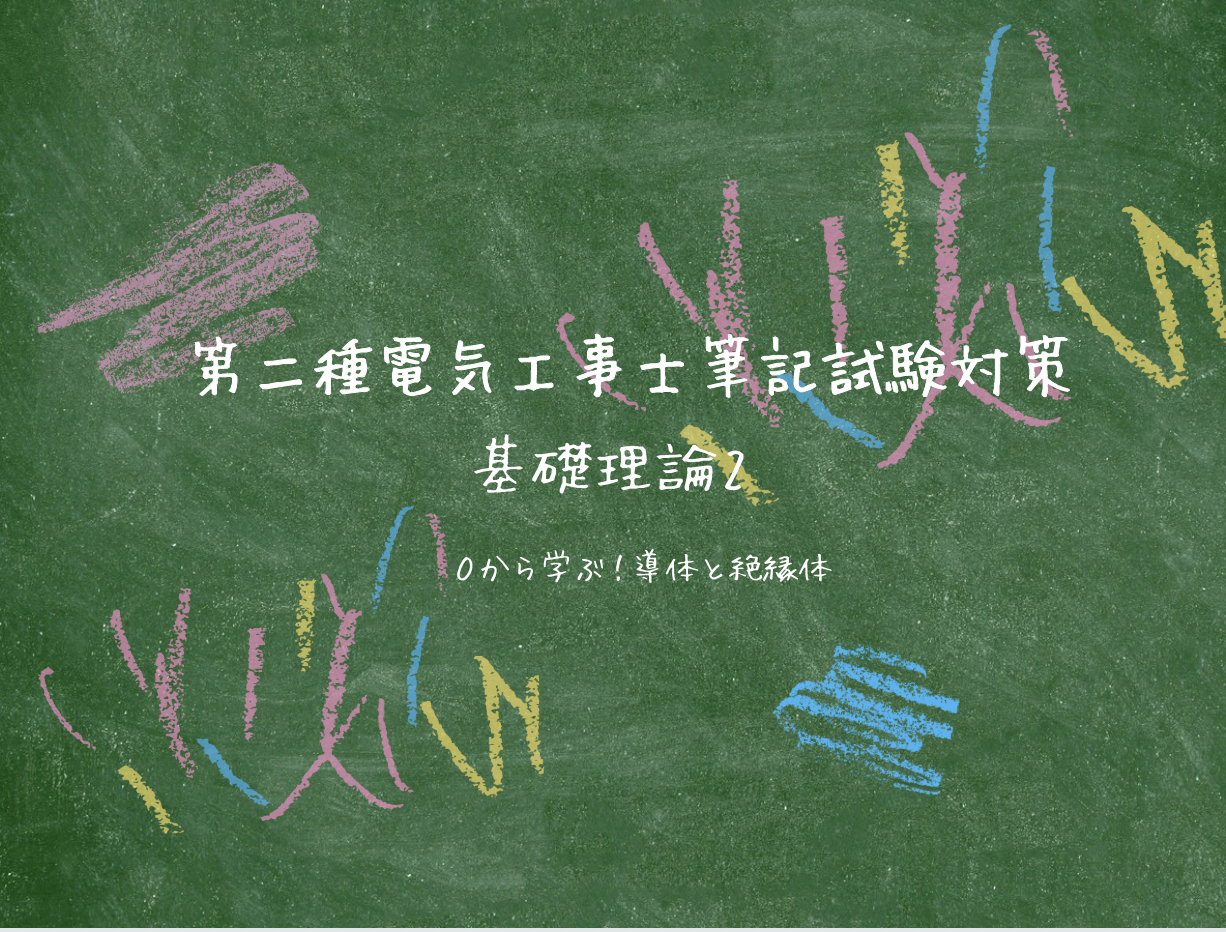電気の資格のアレコレ
電験三種の科目別の勉強方法は?初学者がつまずく3つのポイントを解説

「今度の試験に向けてポイントや勉強のコツについて知りたい」
「電験三種の科目別の勉強方法はどうしたらいい?」
このような悩みを持つ受験生が実は多くいるのです。
電験三種は、4科目それぞれで勉強のポイントが異なります。そのため、各科目のポイントと全体に共通するポイントをおさえて対策することが大切です。
本記事では、電験三種の試験で初学者がつまずきがちなポイントや科目別の勉強方法について詳しく解説します。
目次
電験三種の初学者が勉強で意識すべき3つのポイント

電験三種の初学者の方が意識すべきポイントは、以下の3つがあります。
• 科目ごとの特性を理解して、科目に合わせて勉強方法を変えていく • 独学の場合は掛かる期間や勉強方法を事前にしっかり考えておく • モチベーションを保って最後までやり切る
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
電験三種の科目別に見る勉強方法
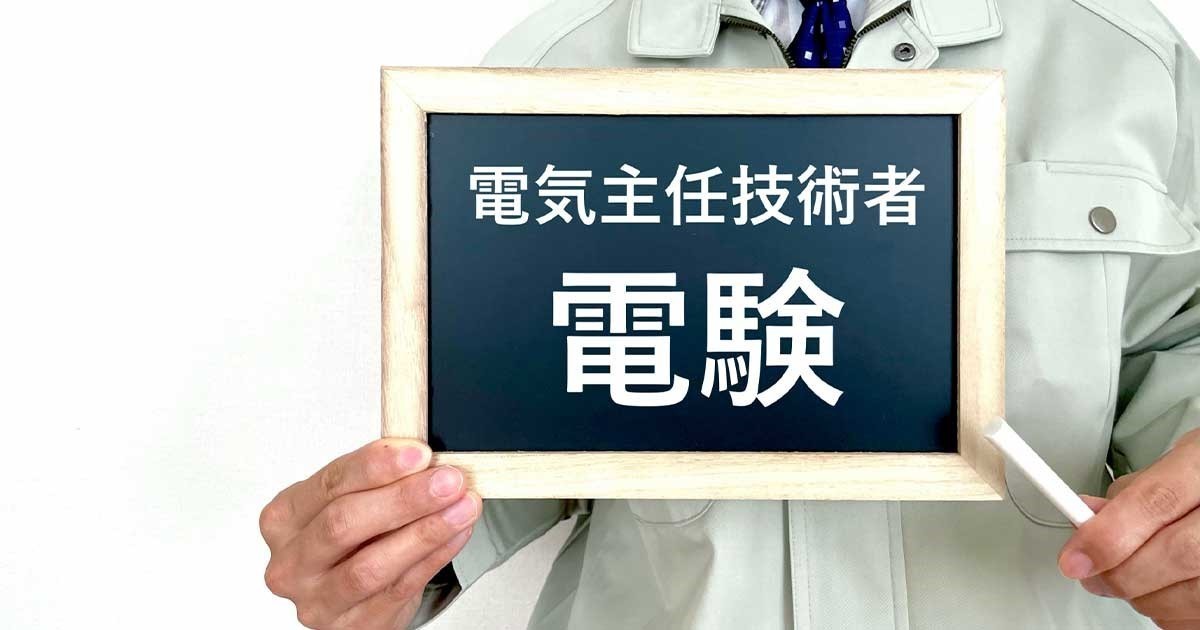
電験三種には理論・電力・機械・法規の4科目があります。 4科目ともそれぞれ特性が違うため、同じように勉強を進めていくと途中でつまずいてしまいます。ここでは、科目ごとのポイントを詳しくみていきましょう。
理論の勉強方法 | 基礎を徹底して計算問題を攻略する
理論には、電気に対する基礎知識が多く登場します。そのため、基礎を徹底して計算問題を攻略することが大切です。
• 直並列回路 • 三相交流 • ブリッジ回路 • フレミングの法則 • 電磁力
上記の分野は、電力や機械、法規の計算問題を解く際にも必要となる知識です。そのため、問題集を繰り返し解いて苦手分野をなくしておきましょう。 理論を攻略したら計算問題を解くための土台部分は完成します。その後は、各科目で必要な知識を勉強して合格する力を身につけましょう。
こちらのページでは、理論の出題内容や出題傾向を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

電験三種の合格を勝ち取ろう!「理論科目の強化書」
8月22日は電験三種の試験日です。本企画では、理論・法規・機械・電力の4科目について、勉強のポイントをお伝えします。
電力の勉強方法 | 送配電から発電の順番で勉強をすすめる
電力は、送配電から発電の順番で対策しましょう。送配電の分野の方が出題率は高く、攻略しやすい分野であるためです。
1. 送電 2. 配電 3. 汽力発電 4. 原子力発電(その他新エネルギー発電) 5. 水力発電 6. 変電所の設計・運転 7. 電気材料
上記は出題率の高い分野を順番に並べたものですが、発電分野は送配電分野よりも出題率は低い傾向です。 電力のテキストを開くと発電分野が最初に記載されていますが、かなり深いところまで勉強したくなる分野です。そのため、まずは送配電分野などを攻略し、その後の残った時間で発電分野の対策をしていきましょう。
こちらのページでは、電力の出題内容や出題傾向を詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

電験三種の合格を勝ち取ろう!「電力科目の強化書」
電験三種の試験日まであと少し。本企画では、4科目のうち、電力について近年の出題傾向をまとめました。
機械の勉強方法 | 公式を暗記ではなく理解する
機械においても他の科目と同様、さまざまな計算問題が登場しますが、大切となるのは公式の暗記ではなく理解です。機械の公式にはよく似たものが登場するため、公式を覚えるだけでは合格できません。
• 直流機 • 同期機 • 誘導機
例えば、回転機だけ見ても上記の3種類が登場します。それぞれで原理が異なるため、計算する際の公式が違うのが特徴です。 そのため、各問題に対してどの知識が必要で何を求めているのか?というものを正確に理解する必要があります。機械で点数を高めるためには、公式をただ覚えるのではなく、原理とあわせて理解しましょう。
こちらのページでは、機械の出題内容や出題傾向を詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

電験三種の合格を勝ち取ろう!「機械科目の強化書」
電験三種の試験勉強を応援するこの企画。この記事では、機械科目について近年の出題傾向をまとめました。
法規の勉強方法 | 毎日コツコツ暗記を継続する
法規は、暗記問題を中心に出題されます。実際の現場でも必要なものが多く登場するため、毎日コツコツ継続して覚えることが大切です。 実際に覚える際は、「エビングハウスの忘却曲線」を利用しましょう。エビングハウスの忘却曲線は人が忘却するメカニズムを端的に表したグラフで、以下のタイミングで復習すると記憶に残りやすいというものです。
• 20分後 • 1時間後 • 1日後 • 1週間後 • 1ヶ月後
また、起床後と就寝前は記憶に定着しやすい時間帯とされているため、覚えやすいタイミングで法規の暗記をコツコツ進めていきましょう。
電験三種の独学での進め方!半年以上は勉強しないと難しい

電験三種は、独学でも合格を狙えますが半年以上の勉強期間を要します。理論・電力・機械・法規の各科目それぞれで1ヶ月半以上の勉強時間が必要となるためです。 例えばテキストで2週間、問題集を1ヶ月半勉強したとしても合計で8ヶ月の勉強期間が必要となります。終盤は過去問対策の期間もあるため、合計で10ヶ月程度は考えておいた方がよいでしょう。
電験三種の勉強時間はどのくらい?1,000時間前後が目安
電験三種の勉強時間は、一般的に1,000時間が目安とされています。これは、1日3時間勉強したとして9ヶ月程度かかる計算です。 実際の電験三種の勉強時間には個人差がありますが、長期的な勉強期間を要するのは間違いありません。そのため、自分でスケジュールを管理して対策する力が必要です。
電験三種を独学で勉強する方法 | テキスト選びから流れを解説
電験三種を独学で勉強する際、テキスト選びからの流れとしては以下の通りです。
1. テキスト・問題集を購入する 2. 理論のテキストから始める 3. 理論の過去問を解き進める 4. 電力・機械の勉強を始める 5. 法規の勉強を始める 6. 試験の2~3週間前は過去問対策を徹底する
テキストを選ぶ際は、イラストと解説のバランスから選びましょう。テキスト選びに失敗すると勉強のモチベーションにも影響するため、じっくりと自分に適したテキストを選ぶことが大切です。
電験三種のモチベーションが下がったときはどうする?5分の勉強から始める
電験三種は長期的な勉強となるため、どうしてもモチベーションが下がるタイミングがあります。そういった際は、5分の勉強から始める方法がおすすめです。
毎日3時間程度の勉強を継続しなければならないと考えていると、勉強を始める前から憂鬱な気分になりがちですよね。勉強を始める時間によっては寝たり起きたりする時間をずらす必要があるため、生活リズムが崩れることもあります。 そういったときは5分だけ始めてみたり問題を1問だけ解いてみたりするとすぐに始めやすいです。中途半端になると続きが気になって継続してしまうため、気づけば1・2時間以上勉強できていることもあるでしょう。
電験三種に合格するため、モチベーションも上手く維持して効率よく対策してください。
まとめ

本記事でご紹介した内容について、ポイントをおさらいしましょう。
• 理論は基礎を徹底して知識をつける • 電力は送配電から始めるのが大切 • 機械は公式の暗記ではなく理解がポイント • 法規はコツコツ継続して暗記する • 独学合格のためには半年以上の勉強期間が必須
電験三種は難易度の高い試験ですが決して合格できないわけではありません。要点をおさえて効率よく勉強を継続することで合格する力は身につきます。 本記事でご紹介した内容を参考に、モチベーションを継続しながら電験三種の合格を目指してください。







 一覧に戻る
一覧に戻る