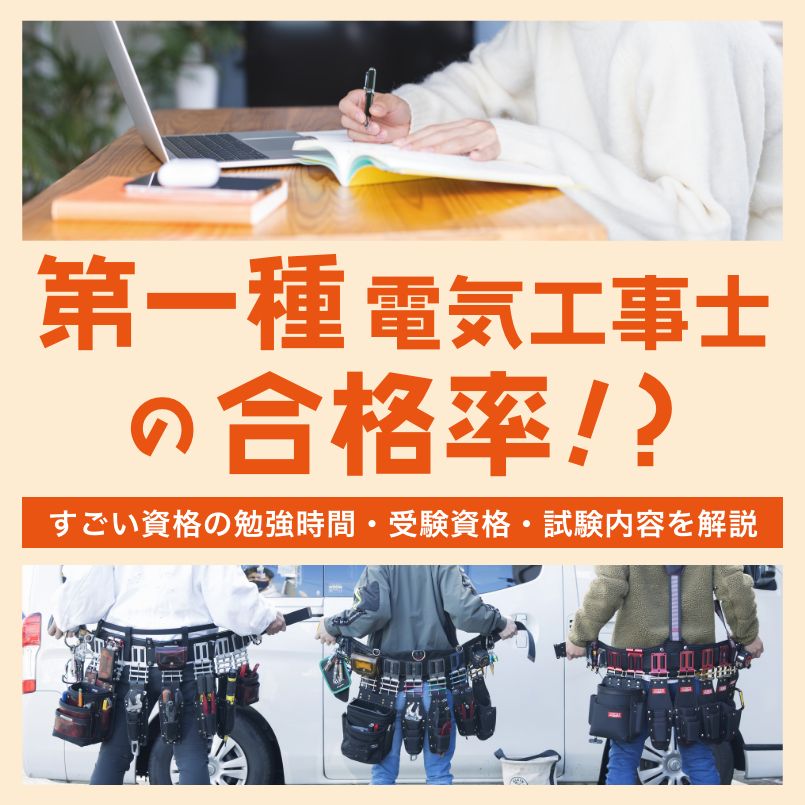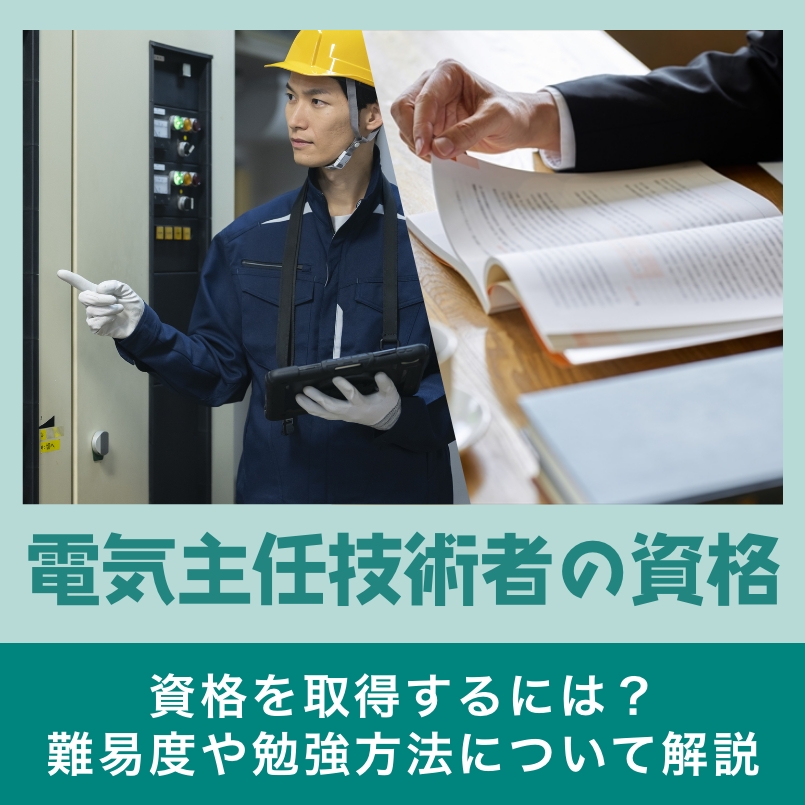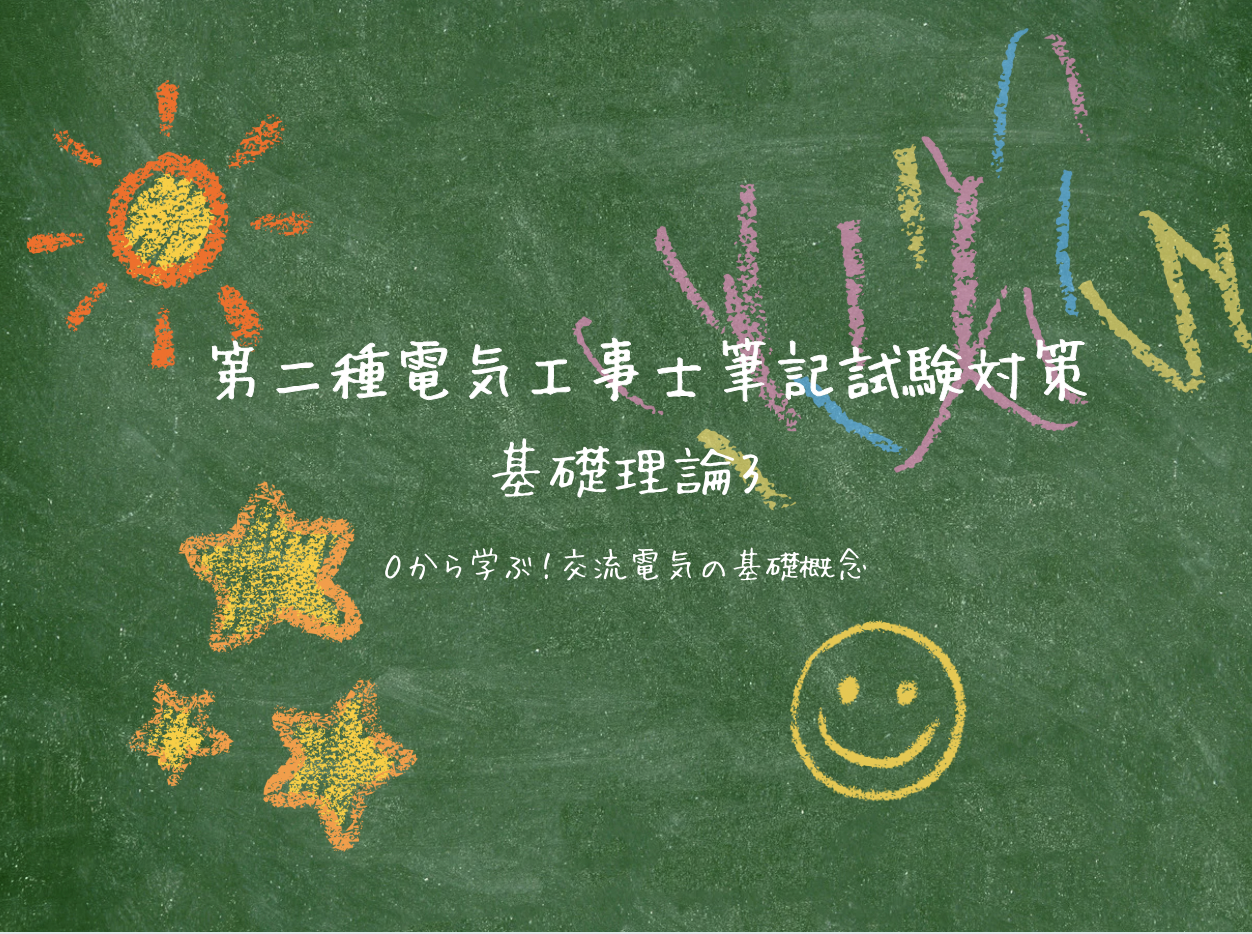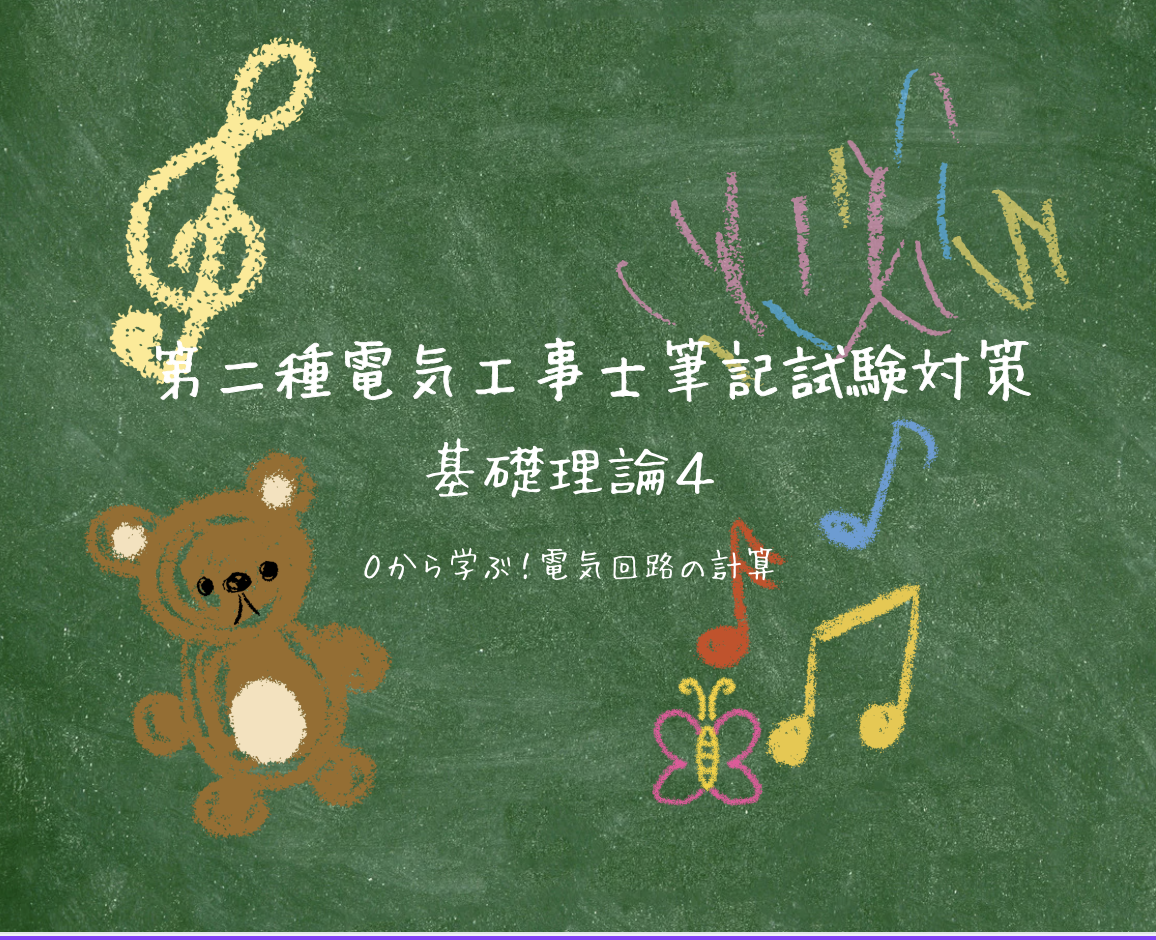電気の資格のアレコレ
独学で「第二種電気工事士」合格を目指す!必要な予算や知識、必要な道具をまるっと解説!

数多くある資格の中でも「電気工事士」の需要は非常に高く、常に人気資格の上位に入ります。就職や転職で有利になるのはもちろん、しっかり実績を積めば独立開業も夢ではありません。
今回は電気工事士に合格を目指すにあたり、必要なコストや知識、道具について丸ごと解説します。
はじめに

電気工事士は独学でも十分合格できる資格です。国家資格のため、資格取得にあたっては準備が必要ですが、対策をしっかり講じれば合格を勝ち取ることができます。はじめに、電気工事士資格を取得するメリットとデメリットについて簡単に解説します。
■メリット
電気工事士は独占業務といって、資格を持っていないとできない仕事が沢山あります。主に電気に関わる仕事は電気工事士の免許が必須となります。電気は今後も絶対的に必要なものなので、電気工事士の需要は高く、生涯活躍できる素晴らしい資格です。一度取得すれば、一生ものの資格となり、更新料も必要ありません(第一種は必要です)。
■デメリット
電気工事の仕事や作業は基本的に立ち仕事が多く肉体労働です。若いうちは問題ないかもしれませんが、歳を取ると負担が大きくなります。また、独学で取得するとなると、受験に掛かる費用は自分で用意しなくてはなりません。
筆記試験対策

最初の壁は「筆記試験」です。
現在、年に2回、筆記試験を受験できるタイミングがあります(詳しくはこちら)。試験の内容自体は異なりますが、難易度は大きく変わらないので、自分の好きなタイミングで受験しましょう。試験内容は大きく分けて「一般問題」と「配線図問題」に分かれます。計50問のトータル6割以上で合格、試験時間は120分です。
■一般問題
電気の基礎的な内容から計算問題、法令に関わる問題などが出題されます。なかでも計算問題は、電卓を使わずにルートを含む計算を解く必要があるので、最初は難しく感じるかもしれませんが、出題される問題は過去問に類似したものが多いため、繰り返し過去問を解くことで自然とコツが身についてきます。また、「識別」といって、写真の器具や工具の名称と用途について問われる問題も多く出題されます。こちらは次の配線図問題でも関わってくる内容なので、電気工事士で出てくるものはある程度把握しておきましょう。
■配線図問題
家やマンションなどの電気配線を図にしたものから出題されます。
これらは、電気工事を行うために必ず必要な見取り図であり、必要な器具や正しい配線や抵抗の値など網羅しながら解いていきます。電気工事士の試験では同じ間取りの配線図が出題されることも多いため、一般問題同様、何度も繰り返し過去問を解く事で対策が可能です。
一般問題と配線図問題に共通するのは、過去問の類似問題が非常に多いこと。つまり、過去問を解けるまで繰り返し挑戦することが合格への近道です。今はインターネットの普及により、過去問と解き方が動画や図入りの解説しているサイトが多くあります。そのため、無理に購入する必要はありませんが、テキストは内容の確認や書き込みするために買っておくと安心です。
勉強期間は最低でも1ヶ月程度、時間に余裕のある人は3ヶ月を目安に計画を立てましょう。毎日、少しの時間でも問題を解くことが重要です。
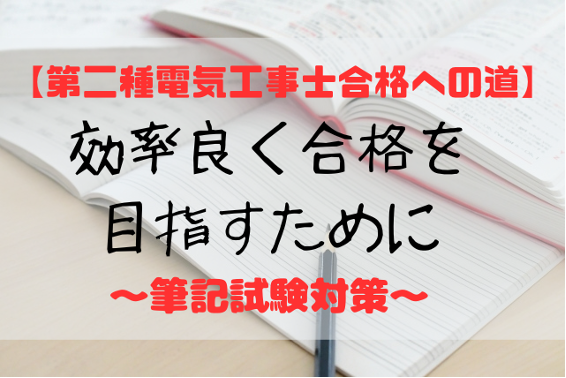
【第二種電気工事士合格への道】効率良く合格を目指すために〜筆記試験対策〜
第二種電気工事士を受験するにあたり、「筆記試験」と「技能試験」の2つの試験に合格する必要があります。最初の筆記試験は最初の壁として、現役学生はともかく長ら…

第二種電気工事士試験の筆記試験合格を目指す!最低限覚えるポイント
前回は第二種電気工事士に最短で合格するポイントについて解説しましたが、今回は筆記試験に着目して解説します。通常、「識別」「計算問題」「配線図」について、あ…
技能試験対策

技能試験は事前に何が出題されるかが公表されるため、事前の対策が可能です。しかし、13問あるうちの1問が出題されるだけで、都道府県ごとに試験内容も異なります。
1番の注意点は、技能試験は1つでも間違えると即不合格になることです。実際の工事で同じようなミスをすると大きな事故につながる可能性があるため、このような厳しい採点基準が設けられています。逆に微細なミスであれば、ある程度は許容範囲となるので、配線の長さなど全て正確に長さなどを揃える必要はありません。しかし、技能試験は40分と短く、時間内に全ての工程を終わらせる必要があります。最後に確認の時間も設けておきたいので、素早く作業する技術も磨いておきましょう。
また、候補問題によって難易度が異なるのもポイントです。とくに難しいと言われる「No7」は試験時間ギリギリまでかかるとの声も。出題される問題は試験が始まる寸前まで分からないので、苦手な問題が出ても焦らないように、どの問題もしっかり対策をしておく事が大事です。
■ポイント
筆記試験から技能試験までの期間は約1〜2ヶ月。筆記試験が終わった段階ですぐに練習に取り掛かり、対策を講じましょう。また、可能であれば電気工事士を受験すると決めた段階で工事用具は一通り揃えておくと安心です。なお、技能試験が不合格でも、一度だけ、電気工事士を再受験すると筆記試験が免除されます。

最短で獲得!第二種電気工事士試験の技能試験対策「最低限おさえたいポイント」
筆記試験と異なり、技能試験は1つのミスで欠陥工事扱いとなり、不合格となります。しかし、事前に問題もわかるため試験対策さえすれば合格は可能ですので、万全の状…

第二種電気工事士技能試験で合格を勝ち取る!”最強”の時短アイテムとは?
これは、第二種電気工事士の技能試験において、時短に繋がるアイテムを紹介していくシリーズです。これらのアイテムがあるのとないのとでは、かなりの時短に影響しま…
合格までに必要な費用

受験の費用
電気工事士を受験するために必要な受験料は、インターネット申し込みが11,100円となり、
トータルで大体4〜5万円程度の費用が必要になります。事前に用意して万全の体制で試験に臨みましょう。
筆記試験
筆記試験ではテキストと過去問、問題集などがありますが、先程も伝えましたがテキストだけ買えば問題ありません。
テキストのみ:1,000〜2,000円程度
技能試験
技能試験で絶対に必要な工具は次のとおりです。
■マスト
・VVFケーブルストリッパー
・持ち手が黄色の圧着工具
■あるとベスト
・プラスとマイナスドライバー
・ペンチ
・プライヤー
・電工ナイフ
これらに加え、コストがかかるのが練習用の器具です。ケーブルやスイッチ、リングスリーブを個別に揃えると高くなってしまいますが、ネットショップでは13問一周分の練習ができるセットも販売されていますので、まずはセットを購入して、足りないものがあれば近くのホームセンターなどで買い足しましょう。もしお近くに電気屋さんがあれば、不要になったケーブルなどを分けてもらえるといいですね。
工具と練習セットの予算:2〜3万円程度
合格後の手続き
合格後は次の4点を準備します。
■合格後に用意するもの
・収入印紙5,300円(都道府県によっては現金書留)
・証明写真
・住民票
・切手を貼った返信用封筒
免許申請をする際は6,000円程度がかります。自分の都道府県の公式サイトをご確認下さい。
まとめ

未経験であっても、しっかり試験対策を行えば必ず合格する事ができる試験です。受験しようか悩んでいる方は、この機会に是非挑戦してみて下さいね。







 一覧に戻る
一覧に戻る