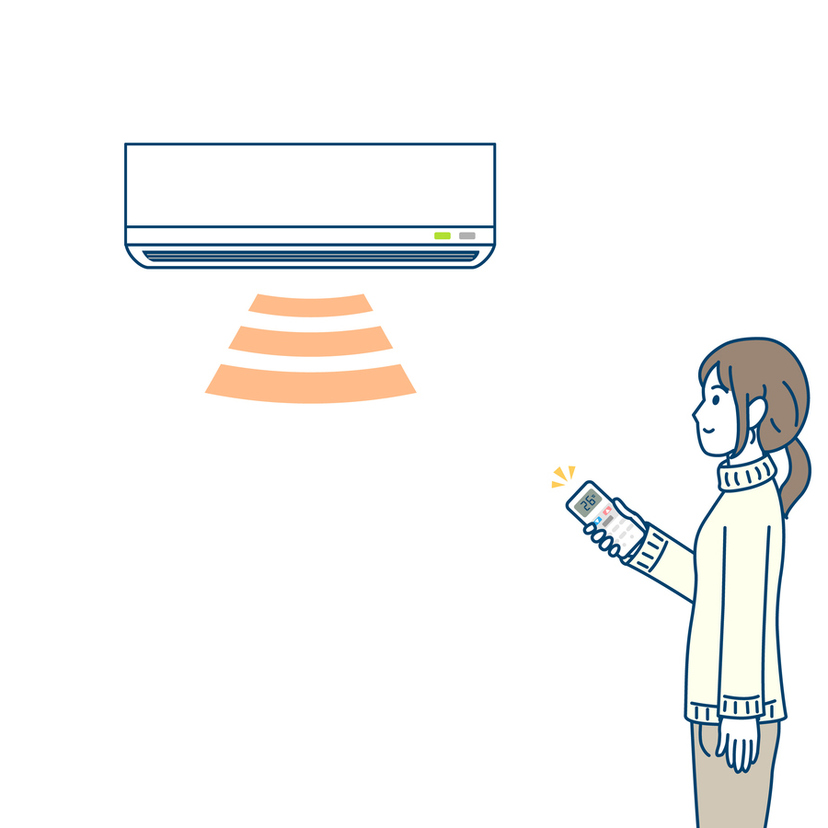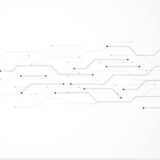クーラー病とは?原因と症状
クーラー病(冷房病/エアコン病)とは、夏の外気温とエアコンのきいた室内との寒暖差が原因で起こる不調の俗称です。
人間は常に外部環境に対応し、体内環境を適切な状態に保つ必要があります。この調節作業を自動的に行っているのが自律神経です。寒い環境では、体内の熱を逃さないように交感神経が優位になり、血流を低下させます。指先や手足から冷えるのは、臓器のある体幹を優先的に体温低下から守るためです。
エアコンを使用する時期には室内温度と外気温に差ができます。外は茹だるような暑さだったのに、屋内に入ってしばらくすると寒さに震えてくる。そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。寒暖差のある環境では自律神経が体温調節に大量のエネルギーを消費するため、身体に疲労が溜まります。そして、疲労の蓄積が頭痛やだるさとなってあらわれるのです。
主な症状・「夏の冷え性」に注意
寒暖差に身体が疲弊してくると、自律神経に乱れが生じ、以下のような症状があらわれます。
冷え
首・肩こり
めまい
だるさ
腹痛・下痢
頭痛
手足にしびれ
食欲不振
とくに女性は男性に比べて筋肉量が少なく基礎代謝が低いため、冷えを感じやすいとされています。寒暖差による自律神経の乱れから冷え性を悪化させる場合もあるので注意が必要です。

エアコンで身体を冷やしすぎない3つの工夫
「クーラー病」を予防するには、身体を冷やしすぎないように、次のような対策をしましょう。
①エアコンの風は「上向き」に設定する
直風は、身体を必要以上に冷やしますので、自宅ではエアコンは上向きに固定し、直当たり避けましょう。暖かい空気は上に、冷たい空気は下にたまる性質がありますから、風向きを上に設定するれば、対流を生み出し、ムラのない室内温度にすることができます。
オフィスでは個人が自由に空調設備を操作できない場合があります。風の直当たりが気になる時は、冷えが悪化する前に、デスクの場所を移動する、膝掛けを使用するなど、事前に対策を取りましょう。

②防寒グッズ・羽織れるものを用意する
エアコンの寒さ対策には、ワイドタイプのストールが活躍します。デスクワークの時は首回りに巻いたり、ひざに掛けたりして肌寒い部分を冷風から守りましょう。また、夏場は電車やスーパーマーケットなどでもエアコンが稼働していますが、ストールを肩から羽織れば簡単に体温調節ができます。そのほか、UV対策にもなる薄手のカーディガンや、足元を保護するレッグウォーマーなどもオススメです。
③ストレッチで血流を改善する
デスクワークを主とする方は、寒さに加えて長時間同じ姿勢で座っていることも血流を悪化させ冷えを招く原因になります。一定時間ごとに立ってストレッチを行い、血の巡りを良くしましょう。
クーラー病・冷え性を予防する3つの習慣
エアコン対策を行いつつ、運動不足や睡眠不足といった自律神経のバランスを乱す原因になる生活習慣も見直していきましょう。
①運動・ストレッチを習慣的に実施する
適度な運動習慣は自律神経を整えるために欠かせない要素です。
特に、ストレッチは凝り固まった身体を伸ばし、副交感神経を優位にしてリラックスモードに導いてくれます。効果的なタイミングは夜の入浴後です。血行の良い状態で実施することでストレッチの効果が高まり、その後の質の良い睡眠につながります。
また、筋肉量を増やすことで体温維持を担う基礎代謝を高めることができます。基本的に筋肉は何もしないと加齢とともに減少していき、基礎代謝も低下していきます。ウォーキングや筋トレなど、自分が続けられそうな運動を見つけて実践してきましょう。

②朝は朝食をとる
朝の食事は体内時計を覚醒させ、体温を上げたり、消化・代謝を調整するはたらきがあると言われています。
理想の朝食は、主食と汁物に魚や卵などのタンパク質のおかずがそろったメニューです。魚の缶詰などは、調理不要ですぐに食べられるので忙しい朝にもぴったりです。
朝食抜きが常態化している方は温かいスープから始めてみましょう。胃腸への負担が少なく、内臓の温度を上げることで代謝が高まります。
③夜は湯船に浸かって温まる
夏はシャワーで済ませてしまいがちですが、温かい湯船に浸かることは、血流改善に非常に効果的です。寝つきが良くなり、質の高い睡眠をとることができます。
入浴時のポイントは、39度くらいのぬるま湯に10分程度浸かること。汗をかくので、入浴前後にはコップ一杯程度の水分補給を欠かさずに行ってください。
元記事「頭痛・だるさは『クーラー病』が原因!?エアコンによる冷え対策6選」は2021年7月1日にBUSINESS LIFEに掲載されたものです。