食欲って何だろう?
食欲は、睡眠欲・性欲に並ぶ人間の三大欲求の1つで、人が健康的に生きていくために必要な欲求です。食欲があるからこそ、適切なタイミングで必要な栄養素を摂取し、ストレス発散や幸福感を得ることができます。必要な欲求ではあるものの、嫌なことがあったり、心理的なストレスを受けたりすると、食欲がコントロールできなくなり、増減してしまうという特徴があります。つまり、食欲は心の健康のバロメーターの1つと考えることができるため、安定させることが望ましいのです。

食欲の秋と呼ばれる要因
夏までは、高温多湿の環境から自律神経の乱れや基礎代謝の低下、冷たい食べ物や飲み物の過剰摂取により内臓機能が低下しやすいことから食欲が減ってしまう人も多くいますが、なぜ秋からは食欲が増しやすいのでしょうか。その要因として考えられるのは、おもに次の3つです。
■① 夏バテの影響
暑い夏に夏バテを起こして食欲が低下した場合、少しずつ涼しくなる秋にはその反動で食欲が増すと考えられています。その理由は、気温の高低差により低下していた基礎代謝が、秋頃に向けて高まっていくため、身体はエネルギーを消費して空腹を感じやすくなるためです。また、夏バテで自律神経が乱れると食欲が低下しやすくなりますが、気候が安定しはじめる秋には自律神経が整いはじめ、食欲が回復するとも言われています。

■② 生活習慣の乱れ
生活習慣が乱れることで、食行動にも大きな影響を与えると考えられます。夏休みで食事のリズムや睡眠時間、運動量などが変わってしまうと、生活リズムを戻せずに食欲が増減し、コントロールが難しくなってしまうのです。自律神経の乱れは夏バテに限らず生活習慣の乱れでも生じます。不規則な生活が長引くと食欲が低下することもありますが、生活の変化はストレスでもあり、それを発散するために食欲が増加する場合も考えられます。

■③ セロトニンの減少
秋は夏よりも日光に当たる時間が少なくなる分、気持ちを安定させる神経伝達物質「セロトニン」が減少しやすい時期です。セロトニンが減少すると、気分の落ち込みやすさや食欲の低下が生じやすくなります。セロトニンは、肉類や乳製品などの摂取や睡眠からも増やすことができる物質です。つまり、秋はセロトニンが減りやすいため、食欲を増すことで、心身の健康を保とうとしていると言えるでしょう。
食欲が乱れると、こんな症状が…

このように、季節の変わり目によって、秋は、食べ過ぎや食欲低下などで食欲が乱れてしまうこと少なくありません。食欲が乱れると、心身には次の状態が現れます。
・体重の増加 / 減少
・体力の低下
・嘔吐や下痢
・気分の落ち込み(食べ過ぎたことへの自己嫌悪)
・生理不順(女性の場合) など
一方で、食欲が安定しているとこれらの不調は改善され、心身の調子は整いやすくなります。
食欲の乱れは度が過ぎると、食べ過ぎてしまう過食症や食事を拒否してしまう拒食症にもつながってしまうため、三食食べることを意識しましょう。
生活を整えて食欲をコントロールしよう
夏から秋にかけては、気温の変化や生活習慣の乱れなど生活リズムが崩れやすい時期です。
食欲は人にとって必要な欲求ですが、そのコントロールは簡単ではないため、秋に食欲の乱れが生じないように、夏休みや初秋の生活リズムを整えることが大切になります。意識的なコントロールが難しい欲求だからこそ、「3食食べる」「起床と就寝時間を決める」など生活を整えて、身体の外側から食欲をコントロールしてみましょう。

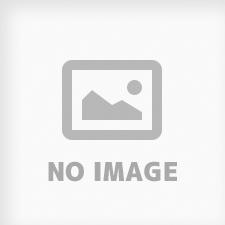













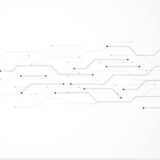









臨床心理士・公認心理師。国立大学院修了後、精神科クリニックや学校現場にてカウンセラーとして従事。専門領域は臨床心理学、心理アセスメント。
また、心理系大学院を目指す人のために『サイコロブログ』にて情報発信中。
https://saikolodsm.com/